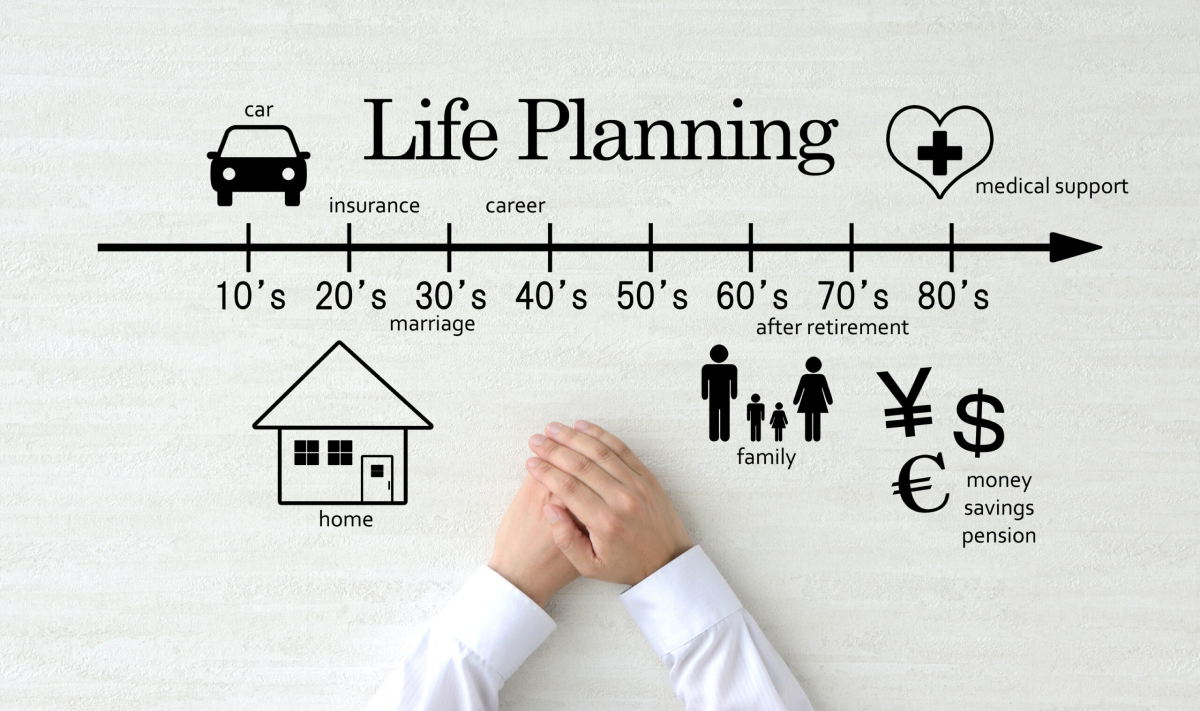「財形貯蓄」という制度をご存知でしょうか?
社会人が継続的に、かつお得に貯蓄をするための制度の1つですが、よく知らないという方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、「財形貯蓄」とはどのような制度なのか、またそのメリット・デメリットは何なのかについてご紹介していきたいと思います。
財形貯蓄とは?
財形貯蓄は、「勤労者財産形成貯蓄」の略称です。ごく簡単に言えば、「給料から一定額を控除(天引き)し、会社と提携した金融機関で貯蓄される」という制度です。勤労者だけが利用できる制度で、雇用する側である会社役員や自営業者は加入できません。また、企業によってはこの制度が導入されていないところもあり、その場合も利用はできません。ですが逆に言えば、制度が採用されてさえいれば、会社の正社員のみにとどまらず、公務員やアルバイト、パート、派遣社員なども利用することができる制度です。

財形貯蓄には、「一般財形貯蓄」、「財形年金貯蓄」、「財形住宅貯蓄」の3種類があります。
一般財形貯蓄
資金目的 :自由
税金 :利息に対して20.315%
契約できる数:複数可
引き出し :預け入れから1年経過後は自由
積立期間 :3年以上
年齢制限 :なし
最も一般的な財形貯蓄で、貯蓄するお金の利用目的が自由であることが特徴です。預け入れから1年は引き出しができませんが、それ以降はいつでも払い出しができます。また、複数契約も可能で、気軽に利用できる財形貯蓄だと言えるでしょう。一方、利息に対しては銀行預金などと同様に、所得税と住民税を合わせて20.315%の課税が発生してしまいます。
財形年金貯蓄
資金目的 :老後資金
税金 :元利合計550万円までは非課税 (*)
契約できる数:1人1契約
引き出し :目的外の場合、過去に遡って課税
積立期間 :5年以上
年齢制限 :開始時55歳未満
財形年金貯蓄は、60歳以降に年金として受け取ることを目的とした財形貯蓄です。60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって受け取ることができます。一般財形貯蓄と異なり資金目的が決められていますが、その分、税金の面で優遇を受けることができます。また、非課税が適用されているため、60歳以降の受け取り金には確定申告が必要ありません。ただし、資金目的外で引き出しを行う際には、過去5年間に遡って課税されてしまいます。一般財形貯蓄と同様の貯蓄型のほか、保険型も存在することも特徴です。
2015年から、財形年金貯蓄の加入にはマイナンバーが必要になりました。
財形住宅貯蓄
資金目的 :持家取得
税金 :元利合計550万円までは非課税 (*)
契約できる数:1人1契約
引き出し :目的外の場合、過去に遡って課税
積立期間 :5年以上
年齢制限 :開始時55歳未満
マイホームの取得やリフォーム資金の積立を目的とするのが財形住宅貯蓄です。財形年金貯蓄と同様に資金目的が定められており、目的外の引き出しを行う場合は過去5年間に遡って課税されます。非課税措置が受けられることや1人につき1契約しかできない点も財形年金貯蓄と同じです。
積立期間については、5年以上とされていますが、5年経過以前に一定の条件を満たす住宅が見つかった場合などは、5年が経っていなくても引き出すことができます。
財形年金貯蓄と同様に、加入にはマイナンバーが必要になります。
(*)非課税措置を受けられるのは、「財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を合わせて元利合計550万円まで」です。
財形貯蓄をするメリット
簡単に貯まる
財形貯蓄の最大のメリットは、給与から自動的に天引きされるために簡単に貯蓄ができることでしょう。意識せずとも勝手に貯金されていくため、「気がつかないうちにこんなに貯まってる!」という楽しみもあります。自分でお金の管理をするのが苦手だという人には、特に嬉しいメリットですね。
銀行預金よりも利率が高い
銀行預金に対するメリットとして、財形貯蓄における利率がやや高めに設定されているということが挙げられます。定期預金と比較すると必ずしも高いとは言えませんが、一般財形貯蓄であれば自由に引き出しができるという点で定期預金にはない便利さがあります。預け入れから1年間は引き出しができませんが、それ以降は普通預金のように使え、普通預金よりは高い金利を得ることができます。
税制面で優遇される
住宅と年金の財形貯蓄では元利合計550万円までは非課税です。銀行などの利息には20.315%の税金が課されていますので、一般的な金融機関にはないメリットだと言えるでしょう。一般財形貯蓄には銀行などと同様に20.315%が課税されるので注意が必要です。
長期・低利の住宅ローンが利用できる
種類にかかわらず、財形貯蓄制度を利用している方は、「財形持家融資」という住宅ローンを利用することができます。財形貯蓄残高の10倍以内で最高4000万円まで、住宅費用の90%までの限度額で、5年間の固定金利で融資を受けることができます。財形貯蓄に加入していないと利用することができない、長期・低金利の住宅ローンです。
7年ごとに奨励金を受け取れる
会社によっては、「財形給付金制度」あるいは「財形基金制度」といった制度を持っていることがあります。そういった制度が存在する会社に勤めている場合、7年が経過するごとに一定額が支給されます。ただし、この制度を持たない会社も多くあるので、事前に確認しておくことがベターでしょう。
財形貯蓄をするデメリット
ペイオフ金額への影響
一般的な金融機関は、倒産した際に普通預金を補償する、ペイオフという制度を持ちます。ペイオフで補償される金額は最高1000万円までですが、自分が普通預金口座として利用している金融機関と、財形貯蓄において会社が提携している金融機関が同じ場合、ペイオフの対象には普通預金と財形貯蓄の両方が含まれます。つまり、普通預金として補償される分が減ってしまうとも言えるのです。おそらく、これが財形貯蓄に関連する最も大きなデメリットと言えると思います。これを避けるために、会社がどの金融機関と提携しているのかは事前に把握しておく必要があるでしょう。
一年間は払い出せない
一般財形貯蓄は普通預金と同じような使い方をすることができますが、預け入れから一年間は引き出すことが出来ません。銀行の普通預金と比較するとやや不便な点ですね。
インフレには弱い
金利が(通常の預金に比べれば高いとは言え)あまり高くなく、基本的に貯金を守って積み立てていくタイプの資産運用なので、インフレへの対応力は高いとは言えません。ただ、このデメリットは、預金全般に言えることです。インフレに強い資産運用としては、投資が挙げられるでしょう。しかし、投資はもちろん危険を伴うものですから、安全性という点では財形貯蓄に軍配が上がります。
その他の注意点
退職・転職するとき
退職すると、新たな積立はできなくなります。役員になるなどして勤労者でなくなった場合も同様です。解約などについては各契約によりますが、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合は、退職して一定期間が経過すると課税の対象になってしまいます。
転職の場合は、新しい勤務先でも財形貯蓄の制度が導入されていれば、引き続き貯蓄を継続することができます。前の職場で使っていた金融機関の取り扱いがない場合もでも、退職から2年以内であれば別の金融機関に預け替えて継続できます。
積立の中断
一般財形貯蓄の場合、契約内容にもよりますが、基本的に中断することが可能です。財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合は、最後の預け入れから2年が経過すると非課税措置が受けられなくなるので注意が必要です。
育児休暇を取得するとき
一般財形貯蓄の場合は、育児休暇の間は積立の中断となり、休業の期間を挟んで継続することができます。
財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄でも、休暇前に所定の手続きを行い、定められた再開日に積立を再開すれば、継続が可能です。
結論
財形貯蓄には様々なメリット・デメリットがありますが、最も大きなメリットはやはり、天引きにより自然に貯金ができることでしょう。
ですから、自分でしっかりお金の管理・貯蓄ができるという人には、あまり必要のない制度かもしれません。

ですが、大きなデメリットもないので、一度試しに使ってみる、というのもアリですね。